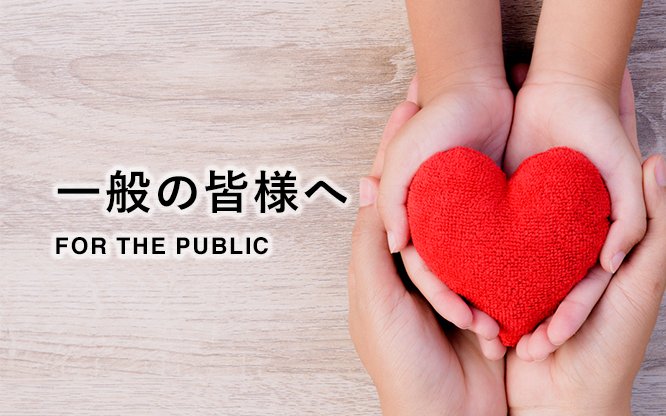リレーエッセイ
2024.08.26
第14回:人工臓器開発に生きるものづくりの魂

作者プロフィール
氏名:穴井博文
所属:大分大学医学部先進医療科学科 学科長
大分大学医学部臨床医工学センター
教授
新年早々、能登半島で震災がありました。思い出せば、私が人工臓器の分野に足を踏み入れたのは和倉温泉で1991年に開催された、「人工心臓と補助循環懇話会」に参加したことが始まりでした。小さな温泉町の中に一際目立つ加賀友禅の大きな幕を掲げた旅館で開催されたことを覚えています。報道でその温泉街が被災している状況を見て心が痛むと同時に、自分のキャリアパスの始まりはここだったことを思い出しました。
その年から国立循環器病センター研究所人工臓器部にレジデントとして勤務し、人工心臓と補助循環の研究に没頭することになりました。当時は体外設置型のTOYOBO LVASの臨床使用が始まったばかりで、研究所では、Total Heartや定常流ポンプを用いた左心補助、人工肺の性能向上などの研究が行われていました。これらの研究の傍らで、私は軸流ポンプを用いた人工心臓の開発研究を始めました。すでに工業界ではターボポンプの技術は確立されたものがあったのですが、人工心臓への応用は研究段階で、特に小型の軸流ポンプは一から作るしかありませんでした。どうやって作るか見当もつかなかったところで、工学の本を読んで、ポンプの設計理論を勉強しました。数値計算をし、自ら図面を引いて設計し、手で真鍮棒から切削してインペラを試作しました。当初、部の同僚からは、そんなもの手で作れるわけないと言われましたが、設計通りの性能が出せることを示し、調子に乗って、次々と様々な回転数で設計し、毎日毎日、朝から晩まで工作室にこもって削り続けました。それを用いて溶血軽減の基礎研究を行い、比速度を無視して10,000回転以下で設計すれば溶血はしないという結論に至りました。
その後米国のTexas Heart Instituteに留学して、Abiomed Total HeartやJarvik 2000の基礎実験などに携わります。この時期の日本人工臓器学会でHeartMateの植え込みを中継するセッションがありヒューストンでの植え込み実験に参加したことは印象的に覚えています。ここでもターボ血液ポンプの基礎研究を続け、小型化が可能で高性能である斜流式血液ポンプの開発に着手しました。家に旋盤やミルを買い込んで、これも手作りで、マグネットカップリング駆動、ピボットベアリングで軸シールのない斜流ポンプを試作し、水力効率67%、溶血も市販の遠心ポンプの半分以下という高性能を示しました。
1996年に帰国し大分で心臓血管外科の臨床に戻り、LVADを用いた重症心不全治療を推進してきました。研究面では産学共同研究で、私が試作した斜流ポンプをモデルに、小型斜流式体外循環用血液ポンプの開発に着手しまし、企画から5年間で製造承認取得、2003年に臨床使用に至るという異例の速さで製品化(JMS Mixflow)に成功し、今も全国で広く使用していただいています。この実績が評価され、2012年に大分大学が「東九州メディカルバレー構想事業」に参画する際に、大分大学医学部の産学官連携の旗振り役として、臨床医工学講座(のちにセンター)教授を拝任し、産学官連携による医療機器開発事業に携わることとなりました。ここでは主に医療機器開発に新規参入しようとする企業研究者の人材育成支援が中心となりました。12年間活動してきた中で医工連携・産学官連携による医療機器開発における課題が浮き彫りになってきました。そのうち最も大きなものは、医療従事者と研究者と企業と行政との意識の相違、温度差です。これを解決するには、医工連携・産学官連携の本質とは何かを再認識する必要があると考えます。医工連携は医学と工学、医療従事者・研究者と工学・企業研究者、医療と技術との連携などとよく言われ、そこでは専門分野・専門業種での分担と協力、および専門知識・技術の提供が行われるとされます。しかし、私はこれではだめだと考えます。業界、領域の垣根を超え、異分野・異業種の世界に積極的に飛び込んで、それらの領域の価値観を理解したうえで、異分野・異業種の知識・技術を自らが学んで習得し、異業種間の情報交換とディスカッション、いわゆるBrain stormingを繰り返し行うことで「異業種の融合」と、「共通の目標」至ってはじめて医工連携は成立すると考えます。そのためにアカデミアに課せられた任務は、医学知識を持った工学者、工学的知識を持った医療従事者、医学と工学の知識を兼ね備えた研究者、言い換えれば「融合人材」の育成であり、それが真の課題であるといえます。産学官連携も同様です。産学官が異業種の融合と共通の目標に至って初めて産学官連携が成し得ると考えます。
もう一つ感じることが医療機器開発のプロセスに変化が起こってきたことです。従来、医療・福祉現場のニーズと企業や大学の持つシーズとのマッチングからスタートし、企画立案、開発研究・試作、検証・治験、製造承認・保険収載を経て製品化、臨床使用に至るのが医療機器開発のプロセスの王道であるとされてきました。ここで行われてきたことはあるニーズに対して一つの企業が秘密裏に進めてゆく、言わばクローズドイノベーションの典型であり、時間と経費を費やしてきました。この10年間の大きな変化の一つはバイオデザインを代表とする、Design thinkingの導入で、もう一つの変化がオープンイノベーションの浸透です。さらに大きな変化が、デジタル技術、AI、データサイエンスです。私が平成時代に行ってきた手作りによる試行錯誤はもう時代遅れで、コンピュータシミュレーション、CFD等により、ポンプ特性、溶血特性、各部のせん断速度などが推測可能となり、コンピュータ上で実機レベルを試作できるようになりました。また熟練の技術者による匠の業は、CNC旋盤、CNCフライス盤、3Dプリンタや光造形に置き変りました、さらに調査や分析は生成AIによって超短時間で可能となり、経験と暗黙知はデータサイエンスにより表現化され、熟練の外科医の手技をAIで再現できる時代になりました。これらのデジタル技術は、「開発研究」の効率化と迅速化と加速化に大きな成果をもたらしました。
今後の人工臓器開発研究は、このようなプロセスの変化やデジタル技術の導入により、我々が取り組んできた時代とは全く異なるのもとしてさらに発展してゆくことが予想されます。そんな時代で活躍する若い研究者の皆さんに伝えたいことがあります。どんな時代になっても「必要なものは自分で作る、創る、造る」、「ものづくりのスピリッツを失ってはいけない」ということです。