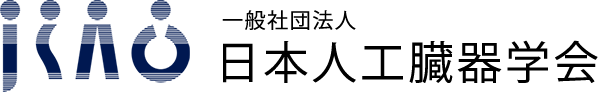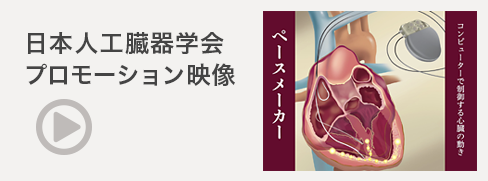リレーエッセイ
2025.10.07
第17回:医療機器開発とPMDA審査
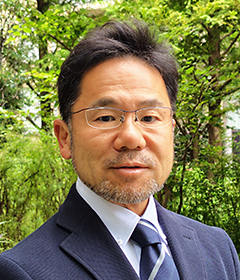
作者プロフィール
氏名:石井健介
所属:PMDA 執行役員 機器審査等部門担当
様々な疾患で苦しむ患者さんを救いたい。そんな想いで人工臓器の開発研究に取り組まれている皆様、あなたが今日、研究室等で積み重ねているデータやアイデアが、いつか実際の患者さんの命を支える医療機器となる。その橋渡しをするのが、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(PMDA)という組織です。PMDAは決して「お役所仕事」の機関ではありません。また、決して研究を拒む「壁」でもなく、むしろ、研究者の情熱と患者さんの希望を繋ぐ「RS(レギュラトリーサイエンス)の担い手」です。
PMDAは厚生労働省(MHLW)のもとで、医療機器の承認審査(品質・有効性・安全性の科学的評価)をはじめ、企業や研究者からの開発相談(助言)への対応、申請資料の信頼性確認、製造所のQMS調査、市販後の安全情報の収集・分析など多岐にわたる業務を担っています。
ここでは、PMDAの審査と相談にフォーカスしてお話したいと思います。
開発された医療機器の最終的な製造販売承認は厚生労働大臣(国)が行い、PMDAの審査結果と専門家の意見を踏まえてMHLWが承認・不承認を決定します。つまりPMDAは審査・助言の窓口、MHLWが承認権限を持つ関係性です。
とは言え、全ての医療機器の審査等をPMDAが行う訳ではありません。医療機器は医薬品医療機器等法(薬機法)に基づき、リスクの程度によってクラスI~IVの4つに分類され、それに応じて審査の手続きが異なります。クラスI(一般医療機器)は、リスクが極めて低く、PMDAへの届出のみで販売が可能です。クラスII(管理医療機器)は、比較的リスクが低い機器であり、このうち認証基準が定められたものはMHLWが認定した民間の登録認証機関による第三者認証を受ける必要があります。クラスIII・IV(高度管理医療機器)はリスクが高いため、PMDAの審査を経て厚生労働大臣の承認を得る必要があります。なお2014年以降、クラスIIIの医療機器でも認証基準のある品目は第三者認証が可能となり、一部の高度管理医療機器は認証で対応されます。このように国内制度では、リスクに応じて「届出」、「認証」(基準適合の確認)、「承認」(PMDAでの審査)の3つに分かれます。
人工臓器は、クラスⅢ・Ⅳに位置し、臨床現場へ届けるためにはPMDAの審査を受ける必要があります。PMDAの審査プロセスは研究開発から社会実装への“関門”であり、その流れや規制を把握することが開発戦略の立案に直結します。規制の初学者であっても、PMDAの審査の基本や相談制度を知ることで、「いつ、何を相談し、どの点を準備すべきか」が見えてきます。
研究開発の現場で意識すべきポイントがいくつかあります。特に、PMDAとの開発相談によって、規制上の論点や必要なデータを早めに確認することは開発の近道と言えます。特に、相談の中でも薬事戦略相談(RS相談)は、アカデミア向けとして今後の開発の道標となるでしょう。「実用化や規制なんてまだ先の話」と思われるかも知れません。しかし、基礎研究の段階からPMDAの視点を理解しておくことで、後々の実用化が劇的に円滑になります。そのため、研究段階から規制を見据えて準備することが、医療機器開発成功の鍵と言えます。
今日あなたがノートに書き留めた実験データなどが、数年後には承認申請資料の重要な一部になるかもしれません。「基礎研究だから」と軽視せず、将来の活用を見据えてデータを整理しておくことの価値は計り知れません。「この実験結果は将来、患者さんへの有効性・安全性を保障する根拠に成り得るか?」、この問いを常に持つことで、研究は学術的成果を超えた「社会的価値」を持つようになります。一方、PMDAを少しお知りの方の中には、「PMDAは怖い」、「審査で厳しく指摘される」、そんなイメージをお持ちかもしれません。しかし、PMDAの審査担当者の中には研究者出身もいます。彼らもまた、革新的な医療技術が患者さんに届くことを心から願っています。早期からのPMDAとの相談は「互いを理解する」絶好の機会と言えます。
まずは今あるデータを整理し、開発コンセプトや今後の試験計画を文書化し、恐れずPMDAの相談窓口にアクセスすることをお勧めします。PMDA公式サイトでは医療機器の相談制度や様々な評価指標などのガイダンスが紹介されていますので、気軽にアクセスして見て下さい。将来の承認審査を意識した研究開発の進め方を身につけ、規制当局との対話を重ねることが、安全で有効な医療機器を一日でも早く患者さんに届けることにつながります。
医療機器の承認を得ることが出来ない条件として、薬機法では「効果又は性能を有すると認められない時、又は効果又は性能に比して著しく有害な作用を有することにより、医療機器としての価値がない時」と規定されています。すなわち、リスク・ベネフィットのバランスを確認することが審査の基本となります。医療機器の開発は医療現場のニーズがスタートと言われ、開発された製品には必ず開発コンセプトがあるはずです。承認に向けたPMDAとの対話で重要な事は、開発製品の「開発コンセプト」と「臨床的位置づけ」です。
「開発コンセプト」とは、医療現場のどのような課題を解決したいのか、そのためにどのような工夫や改良などを行ったのか、既存治療に比べてどのような有効性・安全性の向上を見込んでいるのかという事であり、重要な点です。また、「臨床的位置づけ」とは、開発製品が市場に出た際の既存治療との住み分け(既存治療と同じ位置づけなのか、全く新しい位置づけなのかなど)についてです。これらの点を明確にしておくことで、PMDAと申請に必要な要求事項(非臨床試験や臨床試験の評価項目など)について、よりスムーズに建設的な議論ができます。
承認審査は、遠い世界の話ではなく、皆さんの研究活動の延長線上にあります。ご自身の研究が将来どのように評価され、医療に貢献するのかを意識することが、革新的な医療機器開発の第一歩となるでしょう。今日助ける事ができない患者さんを明日は助けてあげたい、それこそが様々なハードルを乗り越える原動力です。PMDAは、あなたの研究成果を迅速かつ確実に患者さんに届けるための「パートナー」であり、状況等を踏まえて適切なアドバイスをする「三塁コーチャー」でもあります。このリレーエッセイが、皆様と規制当局との懸け橋となり、活発な対話を通じて革新的な国産医療機器が一日も早く社会に届く一助になればと思います。
後記:十数年前のデバイス・ラグの全盛期から植込み型LVADの承認、レジストリ(J-MACS)の構築、そしてJ-MACSを活用した承認審査、DT適応の承認など、産学官が協働・連携すれば様々な課題を解決し、より良い方向に進める事ができることを学びました。
この場を借りて日本人工臓器学会の皆様に改めて感謝の意を表します。